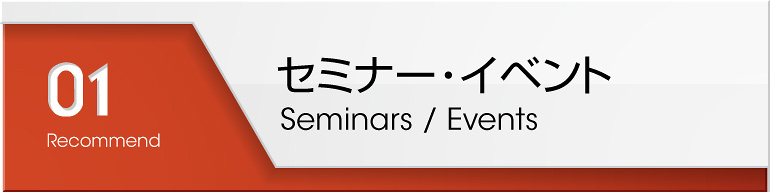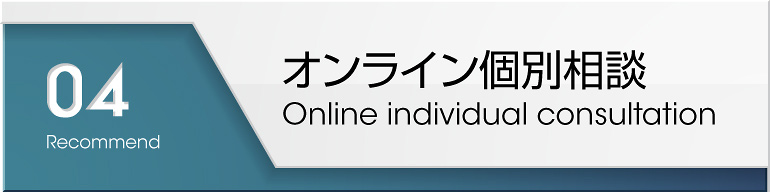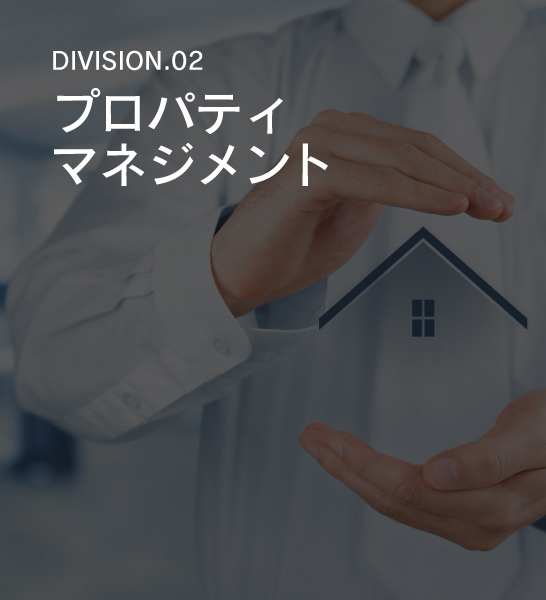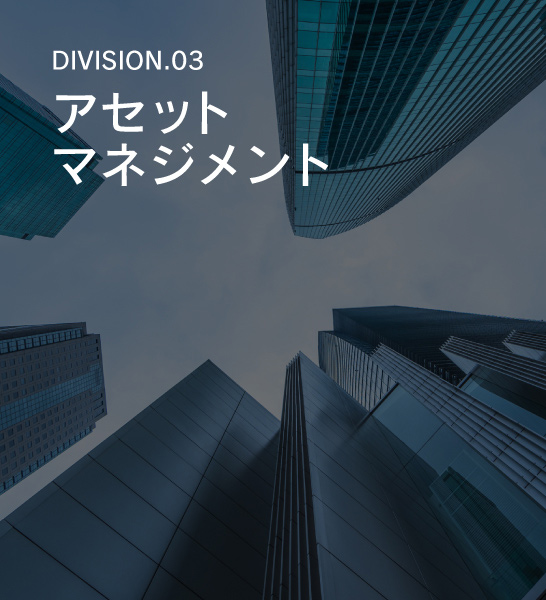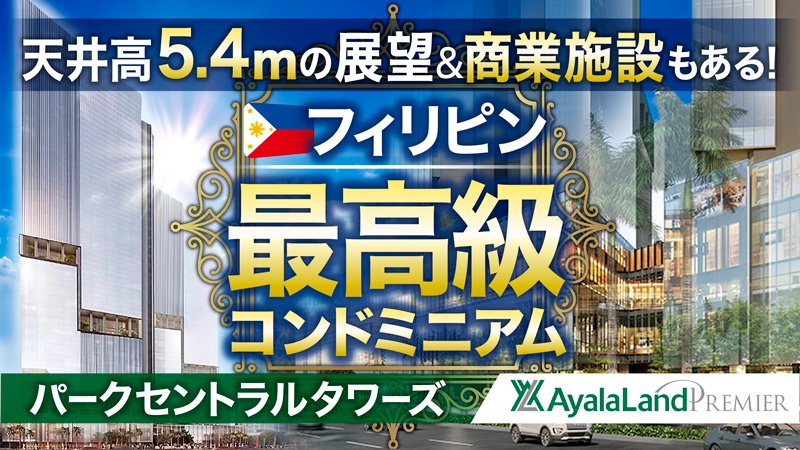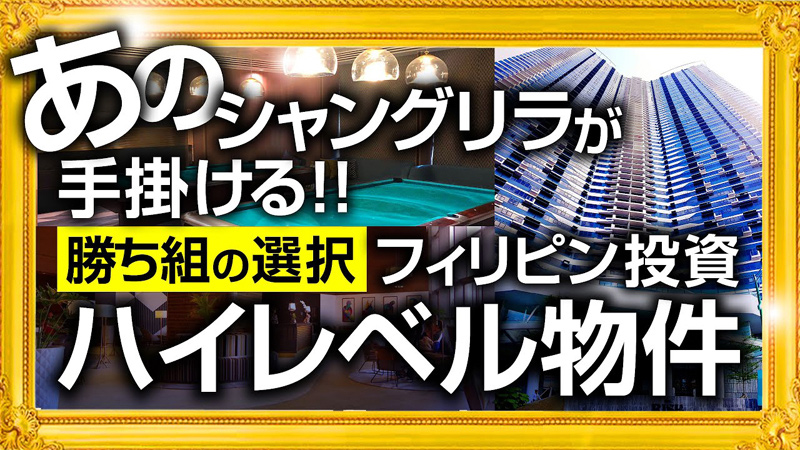節税を目的に、海外不動産を保有している方は少なくありません。
しかし、2020年の税制改正を機に日本では、海外不動産の減価償却を利用した損益通算ができなくなりました。
そんな中、今後の海外不動産の扱いにおいて、方向性を決めかねている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、海外不動産の減価償却が成立していた背景と税制改正の内容を解説したのち、すでに海外不動産を所有している場合の対策についてまとめました。
海外不動産のメリットにも触れているので、海外不動産投資を検討している方もぜひご覧ください。
海外不動産を購入した際に減価償却はできるのか

海外不動産は富裕層に人気の投資先ですが、その理由として以下の2つが挙げられます。
- 減価償却により節税できる
- 中古の資産価値が落ちにくい
海外不動産の減価償却費は日本での所得と損益通算できることから、形式上、課税所得価額を減らすことが可能でした。
減価償却費を計算するために用いる耐用年数は、税法により定められており、この法廷耐用年数は海外の建物にも適用されます。
中古資産であれば簡便法が用いられるため、耐用年数は「法廷耐用年数×0.2」で算出。
短い耐用年数で減価償却できるということは、減価償却費の増額につながるため、海外不動産所得における損失が出やすくなります。
この損失をほかの所得と損益通算することで、課税所得価額が減り節税につながるのです。
また、日本とは違い海外では、中古物件における需要が落ちにくいこともポイントの1つ。
地震が少なく建物の劣化が緩やかなことやリノベーション文化であることなど、中古でも受け入れられやすい風潮が根付いていることが理由に挙げられるでしょう。
そのため、日本では、中古の海外不動産に投資する動きが少なくありませんでした。
しかし、海外不動産投資を活用した節税対策は、2020年の税制改正を機に通用しなくなったのです。
引用元:財務省|令和4年減価償却資産の耐用年数等に関する省令
2020年の税制改正で海外不動産の減価償却に与えた影響
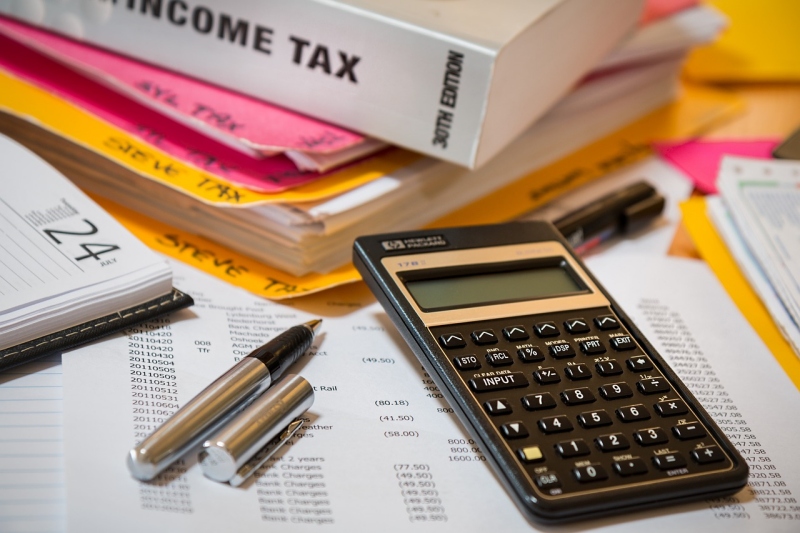
海外では、中古物件における資産価値の認識が日本とは異なっていると前述しました。
中古資産の価値が落ちにくい海外の不動産を、日本の法廷耐用年数に当てはめている体制が問われたのです。
その結果、2020年度の税制改正により、以下の特例が新設されました。
個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
引用元:財務省|令和2年度税制改正の大綱
つまり、2021年以後の所得計算にあたって海外不動産における所得に損失が出た場合、その額が減価償却費に相当する分に関しては、経費として計上できないということです。
この特例を受けたことで、海外不動産投資のメリットでもあった節税には期待できなくなりました。
海外不動産を所有している場合の対策3つ

減価償却による節税が見込めない状況下で、海外不動産をどのように扱うべきか頭を抱えている方もいることでしょう。
ここでは、海外不動産を所有している場合の対策を3つ紹介します。
- 売却する
- 保有し続ける
- 海外不動産を増やして損益通算をする
対策①:売却する
第一に、所有している不動産を売却する方法が挙げられます。
海外では、不動産の耐用年数が日本に比べて長く、築年数が長い物件においても資産価値があるとされています。
日本の場合、法廷耐用年数を越えた不動産は著しく価値が下がりますが、海外の場合は下がるどころか、減価償却の対象としていない国もあるほどです。
そのため、築年数が長くても、不動産価値が安定しているケースは珍しくありません。
経済成長率が右肩上がりの国ではなおのこと、人口増加に伴う物件の需要が高まるため、今後の不動産価格の値上がりが見込まれます。
不動産価値が伸び悩んでいる日本に比べて、海外不動産の方が、売買差益(キャピタルゲイン)を得られる可能性は高いといえるでしょう。
対策②:保有し続ける
家賃収入を目的に、海外不動産を保有し続けることも対策の1つです。
先にも述べたように、築年数の長い物件においても資産価値が下がりにくく、物件が古いという理由で需要が激減するケースはほとんどありません。
築年数経過に伴う入居者減少のリスクが少ないことは、日本の不動産運用と大きく異なる点といえるでしょう。
特に、人口が増加している国では、より需要が高まり安定した家賃収入が見込める場合も。
需要がある物件を選んでいることが前提ではありますが、節税という観点から離れて、家賃収入をベースとした資産運用にシフトすることも有効です。
対策③:海外不動産を増やして損益通算をする
2020年の税制改正による減価償却の規制は、海外不動産所得と日本の所得の合算に限った内容です。
つまり、海外の不動産同士であれば、損益通算が可能に。
たとえば、新たに購入した海外不動産に損失が出ても現在所有している海外不動産が黒字であれば、それらを合算することで、損失を最小限に抑えられるでしょう。
ただし条件によっては、日本での確定申告が必要となる場合があることと、当該国での税務手続きが複雑になる点に注意してください。
海外不動産の3つのメリット

海外不動産に見られる利点は、節税効果だけではありません。
海外不動産投資を検討して入る方は、以下3つのメリットにも注目しましょう。
- 高い利回り
- 分散投資でリスク分散
- 低い投資額で投資可能
メリット①:高い利回り
海外不動産は日本に比べて、家賃収入(インカムゲイン)と売買差益(キャピタルゲイン)の両面における利回りの高さが特徴です。
今まさに経済成長を遂げている国では、人口増加に伴う物件の需要が高まるだけでなく、所得水準の向上により家賃の上昇も見込まれるでしょう。
物件の需要が拡大されれば不動産価値そのものの上昇にも期待でき、売却益を得られる可能性もあります。
実際に各国の利回りを見てみると、2023年現在、日本の利回りは2.7%という結果に。
一方、フィリピンでは3.1%、マレーシアでは4.3%と、東南アジア圏の利回りが日本より高い水準で推移していることが分かります。
経済成長真っただ中にある東南アジアなら、今後さらなる値上がりにも期待できるでしょう。
メリット②:分散投資でリスク分散
日本の不動産価格が下落した際、損失を少しでも和らげるためには、海外不動産への分散投資が効果的です。
国内にいくつかの不動産を保有していても、日本の不動産価格が暴落した際には、その影響が集中してしまうことに変わりありません。
不動産投資では、資産の分散だけでなく、国と通貨の分散もポイントの1つ。
海外不動産を保有することで、合理的にリスク分散でき、国内での損失もカバーしやすくなるでしょう。
大きな金額が動く投資において、暴落によるダメージは常に警戒すべき事案です。
海外不動産を保有しておき、不測のリスクに備えましょう。
メリット③:低い投資額で投資可能
低い投資額で始められる海外不動産の中でも、物価が安い東南アジアは、投資物件においても低い価格設定が特徴です。
目まぐるしい経済発展を遂げている同エリアでは、人口増加に伴う賃貸需要の増加も考えられるでしょう。
物価の低さだけでなく、家賃収入における将来性を見越して、投資家からの注目を集めている地域でもあります。
さらに、好景気による物価上昇が実現すれば、安く購入した海外不動産をそれ以上の価格で売却することも可能に。
将来性のある海外不動産投資ですが、発展途上にある現在、低い投資額で始められるのは大きなリターンを見込めるチャンスです。
海外不動産を始めるならフィリピンがおすすめ

2020年の税制改正を機に、海外不動産の減価償却による節税対策はできなくなりました。
現在、海外不動産を所有している場合は、売却して売買差益を得ることや家賃収入を目的に保有し続けること、複数の海外不動産で損益通算するなど、節税の観点から脱した選択が求められるでしょう。
とはいえ、利回りの高さや低い投資額で始められる点は、海外不動産ならではのメリットです。
特に東南アジア圏は、今まさに目覚ましい経済発展の一途を辿っており、投資家からの人気を集めているエリアとお伝えしました。
中でも海外不動産を始めるなら、格安で物件を購入でき、人口増加も見込まれているフィリピンがおすすめです。
以下のYouTubeでは、フィリピン不動産について解説していますので、ぜひご覧ください。
【YouTube】【知らないと失敗する!】フィリピン不動産投資をする前に!
【関連記事】フィリピンの不動産投資を成功に導くポイント3つと注目エリアをご紹介
【関連記事】フィリピン不動産投資のメリット・デメリットや購入手順をわかりやすく解説
【関連記事】フィリピン不動産投資に必要な税金とは?市場の動向・流れ・ローンの可否について
この記事の監修

一般社団法人 フィリピン・アセットコンサルティング
エグゼクティブ・ディレクター
———
慶応義塾大学経済学部卒業後、東急に入社し、海外事業部にて、米国・豪州・ニュージーランド・東南アジアなどで不動産開発や事業再構築業務に従事。
また、経営企画部門にて東急グループの流通・メデイア部門の子会社・関連会社の経営・財務管理を実施した。(約15年)
その後は、コンサルティングファーム(アクセンチュア)や投資ファンド(三菱UFJキャピタル)などで、企業や自治体の事業再構築、事業民営化等の支援や国内外のM&A案件のアドバイザリーを実施し、2018年10月より、GSRにて、日本他の投資家および企業、ファンドなどに対してフィリピン不動産への投資や事業進出のアドバイザリーを行っている。